マイナーな者が同好の士を見つけやすいのがネットだと仮定すると、実社会(これを☆の言葉ではリアルという)=リアルだと、自分の過去を知る者とコミュニケーションしにくいと言ったストレスも、又は社会的条件も含めた外見上の劣等感があるなどでコミュニケーションしにくいといったストレスも、ネットでは大きく軽減される。
それでも学会員であれば、マナーというか、節度と言おうか、やはりそこは堂々とすべきでちゃんとした礼節とピンとしたものを感じさせる作法を伴わなければならない。いっそ学会系は内部同志のコミュニティーに限っては、家族構成・年収・役職等制限を課したら如何だろうか。今の捩れの原因は、一介の床屋(でも何でもいいが、最近有名な話から挙げた)やデイタイム・ワーカーや未活が経営者とやり合うという所にある。職業は何をやっても構わないのだが、彼等が結局その程度の事しか出来ない頭の持ち主だとすれば、知能がかけ離れ過ぎて、話にならなくなる。
そうなるとどうしようもない。組織では顔が見えるから、雑多な階層が混ざって民衆の渦の中で運動が出来るのであるが、ネットではどうも上手くいかない(ように思われる)。
出来たら、リアル組織からも出てって欲しいと思う連中が、残念ながら何人かいるが、これらについては後日。
さて、☆。
リアルと比べて自己紹介の面倒臭さ(リアルでは参照可能な文脈が限られるという意味で「不自由」、文脈が制約となってコミュニケーションしにくくなる者たち)がないので、☆にとってネットとは、かえって「自由」にコミュニケーションできる場ではないか。
ということは、物理的空間に拘束されない空間は参照可能性が乏しいのではない。
たとえ匿名であってもHNをベースにしたコミュニケーションによって、リアルに於ける人間関係の履歴だけを互いに参照し続けるという文脈の閉鎖化が可能になるのだ。 言換えれば、ネットでは☆が☆であり続ける事によって、一応はリアルに於ける人間関係構築に代替可能と看做され得るコミュニケーションスキルが達成されるのだ。
こう書くと面倒だから、これを一言でいうと、☆はとても居心地の良い場をネットに見出したのだ。
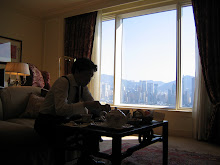
0 件のコメント:
コメントを投稿